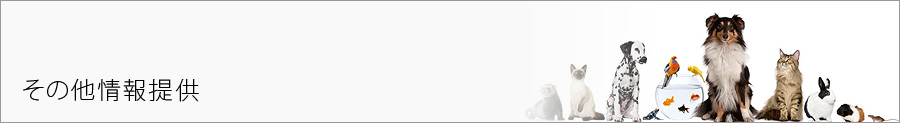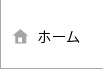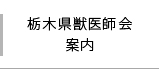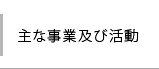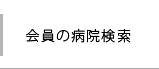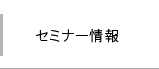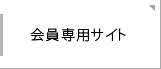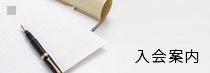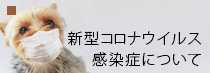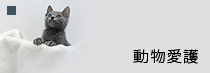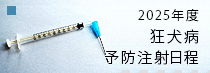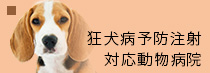カプノサイトファーガ・カニモルサス感染症とは

■Q1 カプノサイトファーガ・カニモルサス感染症とは何ですか?
【A1】
カプノサイトファーガ・カニモルサスという細菌を原因とする感染症です。この菌は動物(イヌやネコなど)の口腔内に常在しています。
この病気は、イヌやネコに咬まれたり、ひっ掻かれたりすることで感染・発症します。免疫機能の低下した方において重症化する傾向のある感染症です。
なお、動物による咬傷事故等の発生数(注)に対し、報告されている患者数は非常に少ないことから、本病は極めて稀にしか発症しないと考えられます。
注)犬の咬傷事故については、保健所に報告されたものだけでも年間約6千件もあり、報告に至らないものを含めるとさらに多く発生していると考えられます。
■Q2 どのようにして感染するのですか?
【A2】
主にイヌやネコなどによる咬傷・掻傷から感染します。
ヒトからヒトへの感染の報告はありません。
■Q3 どのような症状になるのですか?
【A3】
発熱、倦怠感、腹痛、吐き気、頭痛などです。
重症例では、敗血症や髄膜炎を起こし、播種性血管内凝固症候群(DIC)や敗血性ショック、多臓器不全に進行して死に至ることがあります。
なお、重症化した場合、敗血症になった方の約30%が、髄膜炎になった方の約5%が亡くなるとされています。
■Q4 感染しないために、どのようなことに注意すればよいですか?
【A4】
一般的な動物由来感染症予防の対応と変わりありません。日頃から、動物との過度のふれあいは避け、動物と触れあった後は手洗いなどを確実に実行してください。
なお、 脾臓摘出者、アルコール中毒、糖尿病などの慢性疾患、免疫異常疾患、悪性腫瘍にかかっている方、高齢者など、免疫機能が低下している方は、重症化しやすいと考えられますので 特に注意してください。
■Q5 イヌやネコを飼っているのですが、大丈夫ですか?
【A5】
免疫機能が低下していなくとも、咬傷や掻傷から感染し、発症する事例があるため、日頃から、動物との過度のふれあいは避け、動物と触れあった後は手洗いなどを確実に実行してください。
本病だけでなく、一般的な感染症予防のためにも、重要です。
<国内及び海外の発生状況>
■Q6 日本での発生状況はどうなっていますか?
【A6】
日本においては、これまで重症化した患者の文献報告例が14例あります。
その内容をみると、患者の年齢は、40歳代~90歳代と中高年齢が多く、糖尿病、肝硬変、全身性自己免疫疾患、悪性腫瘍などの基礎疾患が見られます。
感染原因は、イヌの咬傷6例、ネコの咬傷・掻傷6例、不明2例となっています。なお、近年の報告が多いのは、臨床現場で本病が認知されてきたためと思われます。
・国内患者の確認報告例(2002~2009年)
発生または報告年 |
患者(性別・年齢) |
感染動物・経路 |
主な症状 |
予後 |
2002 |
女・90代 |
猫・咬傷 |
意識障害 | 死亡 |
2004 |
男・60代 |
猫・掻傷 |
敗血症 | 死亡 |
2004 |
男・40代 |
猫・咬傷 |
敗血症 | 回復 |
2006 |
女・70代 |
犬・咬傷 |
敗血症、DIC、多臓器不全、意識障害 | 回復 |
2006 |
男・60代 |
不明 |
敗血症、DIC | 死亡 |
2007 |
女・70代 |
犬・咬傷 |
敗血症、髄膜炎、意識障害 | 回復 |
2007 |
女・50代 |
猫・掻傷 |
敗血症、嘔吐 | 死亡 |
2008 |
男・60代 |
犬・咬傷 |
敗血症、DIC、黄疸、多臓器不全 | 死亡 |
2008 |
男・50代 |
犬・咬傷 |
敗血症、DIC | 回復 |
2008 |
男・40代 |
犬・咬傷 |
敗血症、DIC | 回復 |
2008 |
男・70代 |
犬・咬傷 |
発熱、創部発赤 | 回復 |
2008 |
男・70代 |
猫・掻傷 |
敗血症 | 死亡 |
2008 |
男・70代 |
猫・掻傷 |
敗血症、DIC | 回復 |
2009 |
女・50代 |
不明(犬) |
電撃性紫斑、四肢末梢壊死 | 回復 |
■Q7 諸外国での発生状況はどうなっていますか?
【A7】
1976年に報告された敗血症・髄膜炎例が、最初の文献報告とされています。
その後、現在までに世界中で約250人の患者が報告されています。敗血症の時の死亡率は、日本国内の患者では30%程度とされていますが、オランダでの近年の大規模患者調査では約12%でした。
また、感染した場合の発症割合については、オランダの調査では100万人に0.7人、デンマークでは0.6人との報告もあります。
<専門家の方へ>
■Q8 診断方法はどのようなものがありますか?
【A8】
患者血液や脳脊髄液、傷口の滲出液を培養して、菌を分離・同定します。培養サンプルからの遺伝子検出(PCR)も可能です。
しかし、医療機関を受診した時に敗血症の状態であることが多く、急激な転帰をたどることや、また、生育が遅い菌であり分離・同定に一定程度の時間を要することから、患者の臨床症状等に応じて早期に適切な治療を開始する必要があります。
なお、血液培養が行える検査施設であれば、分離及びある程度の同定は可能です。
■Q9 治療方法はどのようなものがありますか?
【A9】
カプノサイトファーガ・カニモルサス感染症が疑われる場合には、患者の臨床所見等に応じて早期に抗菌薬等による治療を開始することが重要となります。
咬傷に対する抗菌薬としては、ペニシリン系、テトラサイクリン系抗菌薬が一般的に推奨されていますが、C.canimorsusにはβラクタマーゼを産生する菌株もあるので、ペニシリン系の抗菌薬を用いる際にはβラクタマーゼ阻害剤との合剤などその影響を受けにくいものを選択するとよいとされています。
■Q10 カプノサイトファーガ・カニモルサス感染症と診断した場合に、行政機関への報告は必要ですか?
【A10】
カプノサイトファーガ・カニモルサス感染症は、感染症法の届出対象疾病ではありませんので、保健所等への届出は不要です。
しかし、本菌の調査研究の進展のためにも、国立感染症研究所獣医科学部第一室への情報提供にご協力をお願いします。
■Q11 相談窓口を教えてください。
【A11】
国立感染症研究所獣医科学部第一室(03-5285-1111 内線2622)にお問い合わせください。